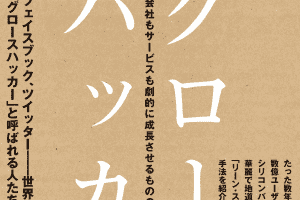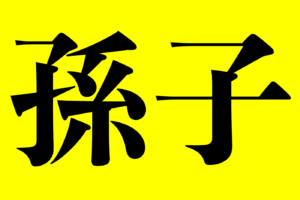「本の逆襲」を要約メモです。
「本の逆襲」というタイトルですが、未来のコンテンツのあり方を問うものでした。おもしろいよ。
出版社も取次も書店も図書館も、本を読む習慣がすでにある人に「この本の面白さ」を伝えるのに精一杯で、誰もその手前にいる人に「本というものの面白さ」を伝えることをしていない。
そもそも何かと何かの出会いというのは、きっかけがあって、偶然に起こる。だから何を「作る」のかといえばそのきっかけ、つまり本と人との「あいだ」にあるものを作るということ。本はただ静かに本棚に並んでいる。そこにどのように人が来て、どのようにその本を手にとってもらうのか、その仕組みを考えること。
「文庫本葉書」に始まる一連の企画には、「本にまつわる多すぎる情報をひとつに絞る」ということ、もうひとつは「一節を引用して切り出して流用させる」というふたつの方法が凝縮されている。
たいていの書店は、ひとつの大きな取次と契約し、その一社から本を仕入れる。
もし本が市場原理にさらされて売上重視の価格競争になってしまうと、たくさんの人が読む本ばかりが作られ、ごく少数の人しか必要としないものは流通しなくなってしまう。そうした事態を避け、多様性を担保しながら、できるだけ日本全国の書店へ安く早く届けるために、このような大規模かつ特殊な流通の仕組みが作られてきた。
もともと書店に特化しているぶん、商習慣が違ったり、ある部分が著しく古いままだったりする。
取次は書店に商品を委託するので、万が一の場合に回収できるように、書店に対して開業時に保証金を要求する。
書店と直接取引をする出版社も増えてきた。本業が出版ではない、デザイン事務所や編集プロダクション、アパレルブランドなどがクオリティの高い本を作り、ごく限られた書店のみで直取引で売っているケースも増えている。
コンテンツそのものに熱狂していて、コンテンツはコミュニケーションのためのネタにすぎない、というのがごく一般的な構図となりつつある。
- 本の定義を拡張して考える
- 読者の都合を優先して考える
- 本をハードウェアとソフトウェアとに分けて考える
- 本の最適なインターフェイスについて考える
- 本の単位について考える
- 本とインターネットとの接続について考える
- 本の国境について考える
- プロダクトとしての本とデータとしての本に分けて考える
- 本のある空間について考える
- 本の公共性について考える
読者の都合からすると、花の種や植木鉢の横にそれらの育て方の本が売っていたり、鮮魚の横に魚料理のレシピが売っていたほうが便利。
最適なメディアやインターフェイスというのは、コンテンツによって違う。本全体を一括りにして、紙がいいとか、電子書籍がいいとかいうのはナンセンス。そのコンテンツにあったメディアを選択し、そのコンテンツに最適化したインターフェイスを設定する。
ユーザーが求めていると同時に「宣伝したい」と考えている側がいるような場合は、真っ先にインターネットに移行していった。「宣伝したい」ものでなくでも、ユーザーが「共有したい」と考える情報であれば、インターネット上にあふれるようになった。
音楽CDの74分という時間がベートーヴェンの第九が収まるようにという理由で決められたが、後に「1枚のアルバムを作るからには60分程度が必要だ」と考える基準になった。しかし音楽CDがデータ配信に移行して、多くのアルバムは1曲単位で購入できるようになった。
この変化になぞられて、本も「1冊の本というからには200ページ程度は必要だ」という発想から離れる必要がある。
フォーマットとして極端に長い単位や短い単位を設定すると、それに適した新しいコンテンツが生まれてくる場合もある。
テキストを読むことによって自分の頭に広がるイメージを純粋に楽しんでほしいという場合は紙、テキストを起点としてインターネット上に広がる様々な情報とのつながりを楽しんで欲しい場合はデジタルにすればいい。このような作り手の発想が必要。
デジタルであれば、翻訳以外にコストをかけなくても、非常に安価に海外に流通させることができる。
翻訳のコストも、これからまだ下がる傾向にある。自動翻訳の精度も少しづつ上がってきている。政府の戦略「イノベーション25」でも、2025年までにコンパクトな自動翻訳機を普及させる見通し。
紙という素材、あるいは本というプロダクトの特性を、電位書籍に触ることで意識させられた。
本の売り方も変わっていく。たとえばデータは200円、紙版は500円、豪華版とグッズのセットは1万円など。
本のある空間は、本を楽しむ人の日常に欠かせないものであると同時に、そもそも本を好きになるきっかけも与えてくれる。
本のある空間は、インターネット上においても、キャンペーンやブランディングのツールとしても成立する。一見本を販売しているようでいて、実際は映画のDVDが売れればいい。
書店よりも図書館のほうが、はるかに長い歴史を持っている。そもそも形を持たない知識や情報は、人から人へと伝達され複製されてもその内容が減るものではない。また、本質的には必ずしも対価を払わなくても人づでに得ることができる。経済学的にも「知識」は「公共財」であると定義されている。「公共財」を生み出す人たちが、きちんと人々に貢献したぶん対価を得られるように、著作権をはじめとする知的財産権を著作物に付与している。
限定的に著作物の再利用を許可するクリエイティブ・コモンズのライセンスや、二次創作を許可する同人マークなど、本を公共へと開くための柔軟な選択肢が生まれている。これらもすべて、本というものが単なる商品にはとどまらないことを示している。
「本屋」は「空間」ではなく「人」であり、「媒介者」のこと。必ずしもリアルの書店を構えていなくても本屋であるというあり方が可能。
下北沢のB&Bでは、毎日イベントを開催すること、ビールをはじめとするドリンクを提供すること、本を並べる本棚を中心とした家具を販売すること、の3つを行っている。
最初は「この人が来るからB&Bに行こう」だった人も、「今日はB&Bに誰が来ているのかな」に考え方が変わる。
少なくともB&Bでは、その場に参加して笑えるエンターテイメントよりは、自分の人生のためになりそうな企画のほうが人を呼べる。
新刊書店としての紙の本を売るビジネスに、相乗効果のある別のビジネスを組み合わせて、収益源を複数確保している。
新刊書店が生き残っていくためには「掛け算型」が最良にして唯一の方法。
数百円の電子書籍を作るのはすでにたくさん選択肢があるが、数万円する限定の豪華本を作る方には、あまりノウハウやアイデアがないように感じる。
「本の逆襲」というタイトルは、ベストセラー「だれが本を殺すのか」や「電子書籍の衝撃」といったネガティブな言葉で煽りを効かせたタイトルへのアンチテーゼ。